事務所の特徴
①島人として大島で生まれ育ちました

高校を卒業するまで、大島で生まれ育ちました。島に深いルーツがありますので、島特有の事情も理解しています。「どこの誰なのか」で不安にさせません。
②実務経験16年以上

新宿の総合事務所に6年勤務し、個人開業して10年が経過しました。実務経験は通算で16年になります(2024年時点)ので実務のトラブルポイントも、勘所も、しっかりと押さえています。長く続けることの難しさを信頼の担保としています。
③様々な専門家と提携し、全ての事案に対応

司法書士・弁護士・税理士など様々な専門家と提携しておりますので、全ての事案に対応可能です。
たらい回しになることのない、窓口は1つだけのワンストップサービスを提供いたします。
プロフィール
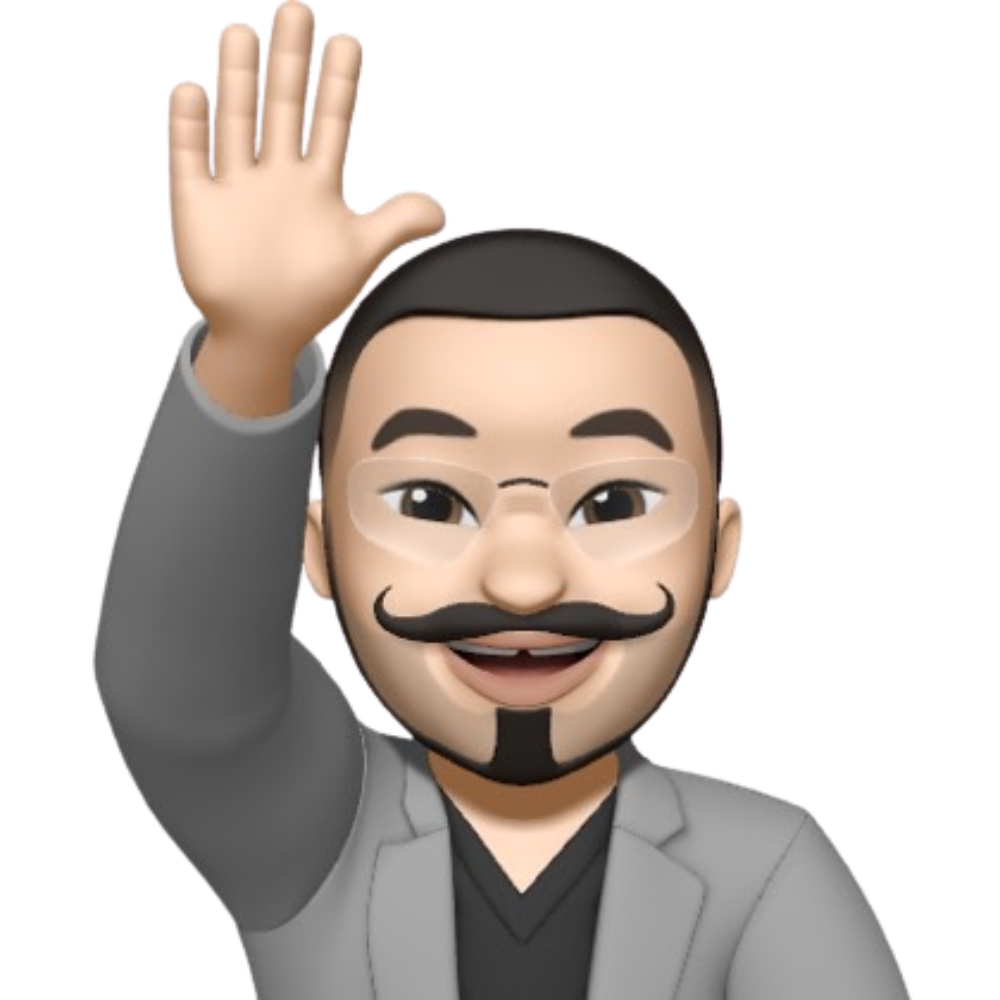
代表 行政書士 冬木洋二朗
職務上の守秘義務を第一に考え、離島特有の事情を理解し、実務にあたっています。法務サービスが行き届いていない伊豆大島に信頼と安心をお届けいたします。
16年のキャリアでほとんどの事案に対応可能です。
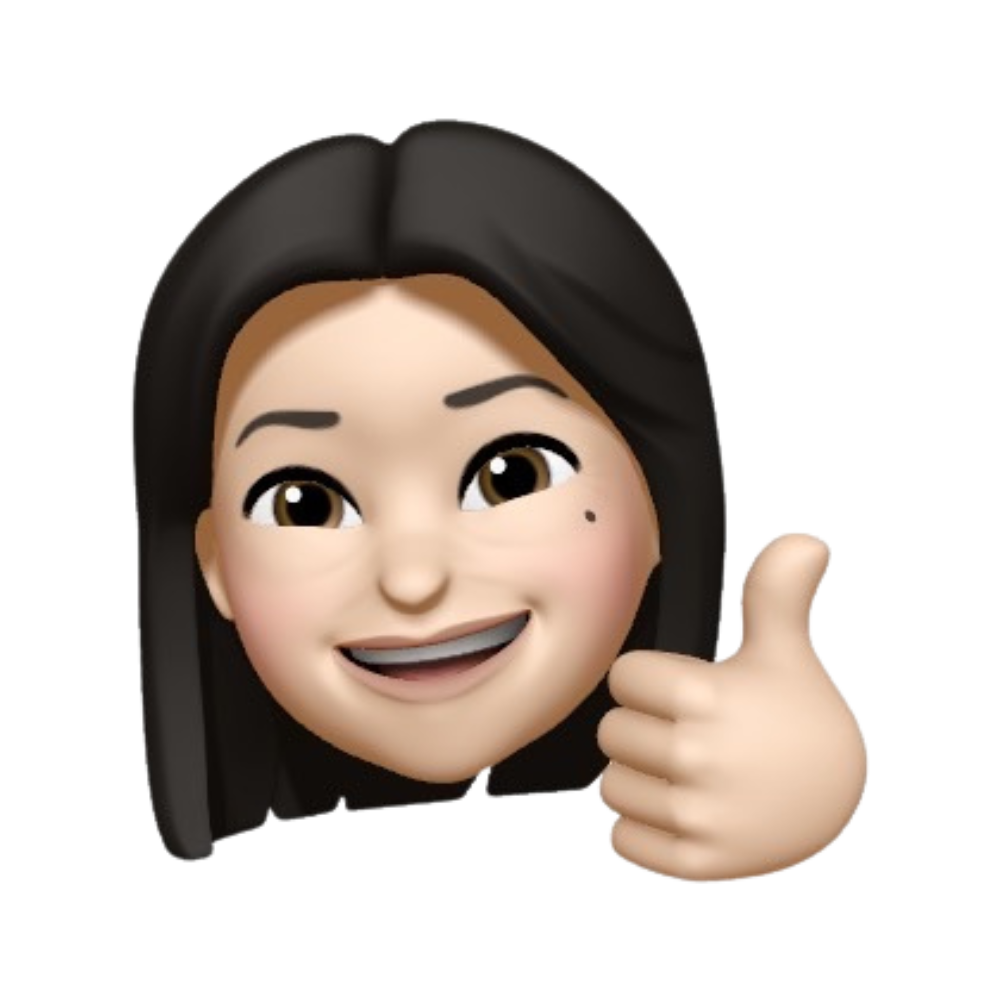
補助者 福井 おりえ
分かりやすい説明と丁寧な業務を心がけております。全力で業務に取り組んでいます。
